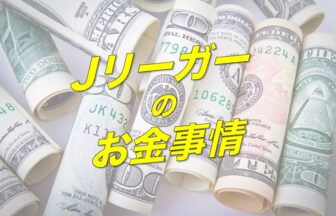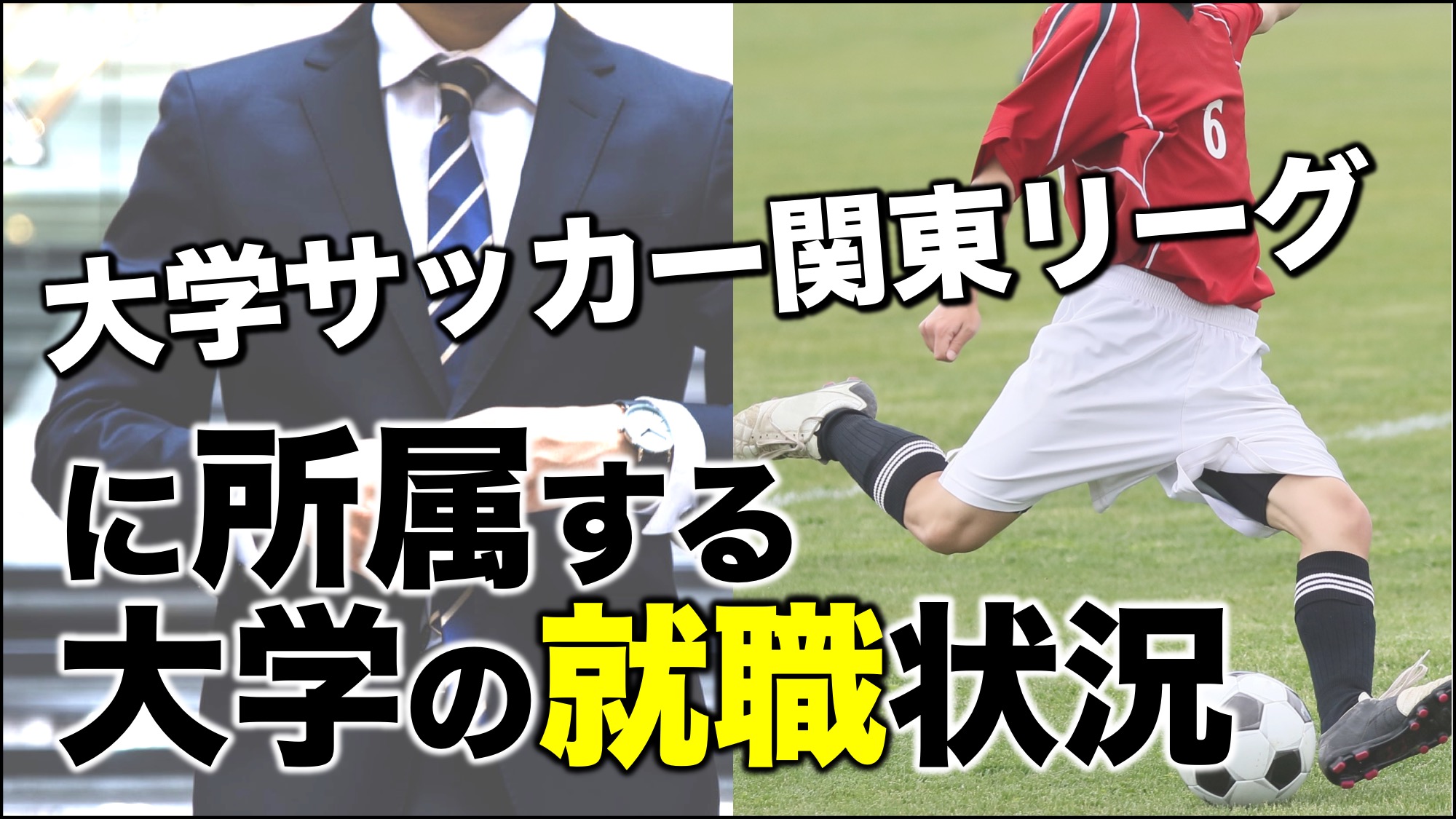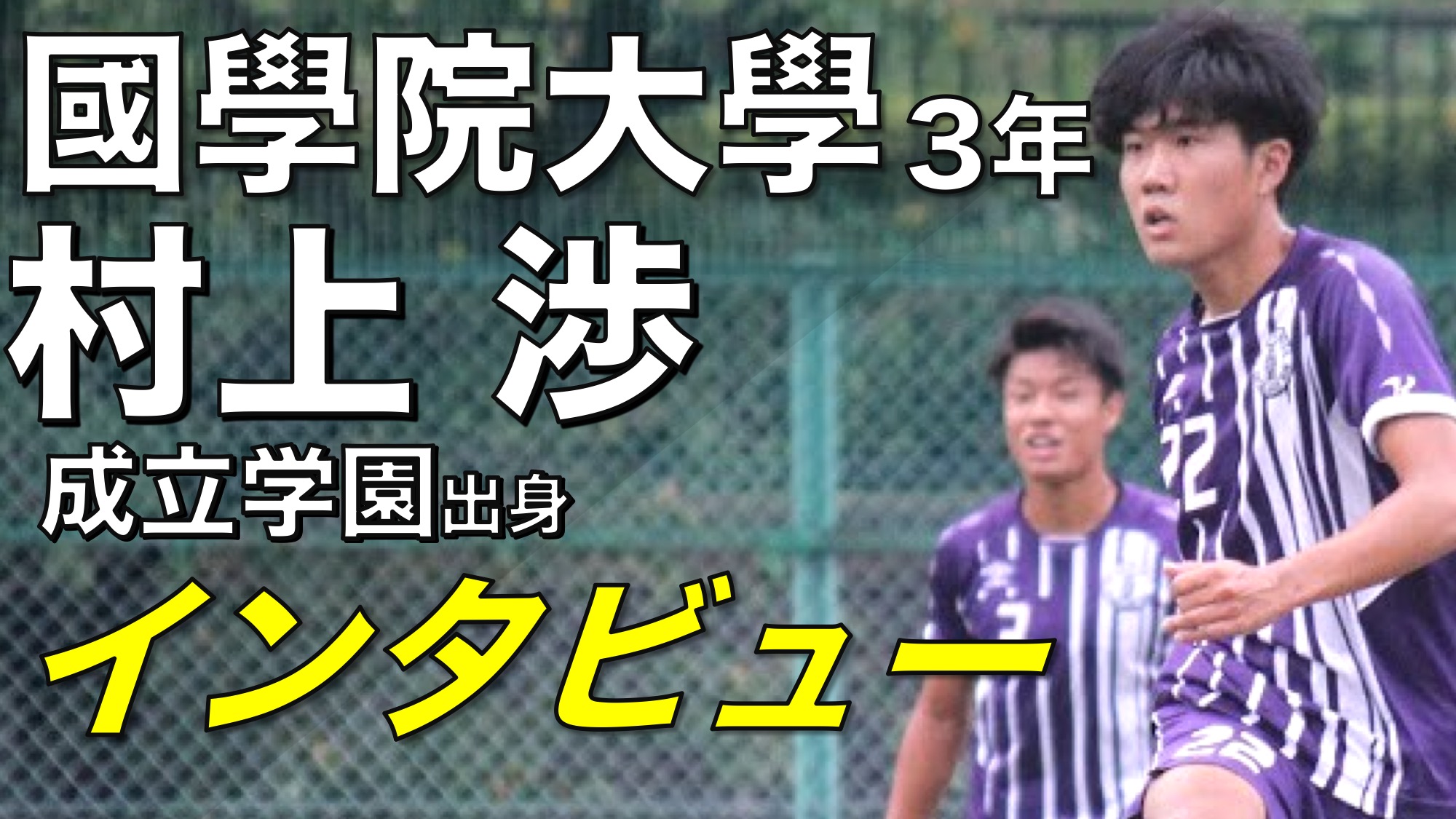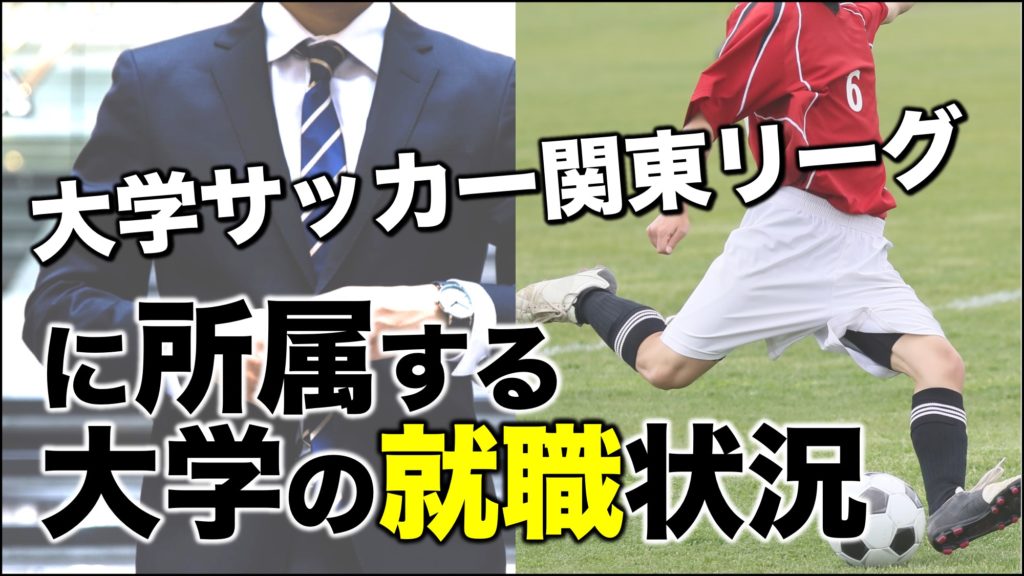今回は常葉大学サッカー部で指揮をとられている山西 尊裕監督に、大学サッカーについてお聞きしました。

プロフィール
お名前
山西尊裕
【選手歴】
1992年–1994年 静岡県立清水東高等学校
1995年–2004年 ジュビロ磐田
2005年–2008年 清水エスパルス
【指導歴】
2009年–2010年 ジュビロ磐田U-18コーチ
2011年 ジュビロ磐田U-15コーチ
2012年 ジュビロ浜松SS監督
2013年-2021年 常葉大学浜松キャンパス サッカー部 コーチ
2022年-現在 常葉大学浜松キャンパス サッカー部 監督
【保有ライセンス】
A級ライセンス
指導者の道へ
ーー指導者になられた経緯について教えてください。
指導者の道くらいしか選択肢がなかったからですね。僕は現役時代から引退後のプランを深く考えていた訳ではありません。選手としてプレーしている時は本当に余裕がある選手ではなかったので。日々の活動で精一杯でセカンドキャリアまで考える暇がなかったです。そういう意味では自分は今の大学生が学業とサッカーを両立している素晴らしさが一番理解できると思います。正直サッカーしかしてませんでした。その日々のトライの結果が14年という年月でした。その結果今指導者としてやらせていただけていると思っています。
ーー大学サッカーを指導するきっかけはなんでしたか?
2つあります。1つはこれは巡り合わせですね。自分は2008年に清水エスパルスで引退し、2009年からジュビロ磐田に戻り指導者を始めました。そこから4年間ユースやジュニアユースを見させていただき育成年代は一通り指導してきたつもりです。そんな中、常葉大学前監督である澤登さんから「常葉大学サッカー部の監督やるんだけど山西、一緒にやらないか」とお話をいただきました。お話の中で「人を育てることができる人間を探している。」という言葉が決め手になりました。自分のことを気にかけてくれて自分としても「これはもうタイミングだ」と思い決断しました。
もう一つは自分が大学に行ったことがなかったことです。大学、大学サッカーってどんなところなのかと想像の域でしかなかったので自分も勉強だ!と思いチャレンジしてみました。

常葉大学サッカー部について
ーー常葉大学サッカー部の魅力について教えてください。
まだまだトライしている最中なのでどこまでできるかはわかりませんが、「常葉大学サッカー部の伝統を創る」ことを目標に活動しています。常葉大学サッカー部で澤登前監督と活動を開始してもう10年目になるんですが、自分たちは「伝統がない」ことに気づきました。関東の大学、今回の総理大臣杯でいえば国士舘大学、国士舘大学サッカー部には伝統があるなと感じました。言葉では言い表せないですけど伝統の中にチームがあるなと。チームの中にずっと続いているものがある。でも常葉大学は監督やコーチが交代する度に歴史がかわり、もう一回新しいものに塗り替えられている気がしていたんです。だからこそ常葉大学サッカー部は自分が指導者ではなくなり次期指導者になったとしても伝統の中での指導。そういうところを目指しています。
澤登前監督と立ち上げて10年目、僕が監督に就任して1年目ですが、まずはそこを引き継げたことは大きいと思っています。その結果としてOB会からも声が上がるようになってきました。地方の大学として「伝統のあるチーム」を目指したいです。関東、関西の伝統のある大学さんと肩を並べられるようなものになろうとトライしている最中です。今回の総理大臣杯では全く届かない位置にいたかというとそうではないけどやはり伝統のあるチームは体制も含めて揺るがないものがあるなと感じました。それを肌感覚で体験することができて選手にとっても、自分にとってもいい勉強になったと思います。
また、今年特に大事にしていることがあります。それはビジョンを描くことです。ビジョンはどこの組織も作ると思うんですよ。ただ言葉だけが泳いでいるなと感じることもありました。だからうまく行かないのかなと。大学には建学の精神があるように部活動にもスローガンがあります。でもビジョンを打ち立てたから何かが起こるわけではなくて、打ち立ててそこを帰る場所にすることで意味が出てくると思うんですよ。意外にもそれが帰る場所になっていない組織が多いなと感じました。これは一般的な会社組織にも言えることなんじゃないかなと僕は思っています。とにかくそこを帰る場所にしてそれを元に全てを進めていくことがすごく大事なんじゃないかなと思ってトライしている最中です。
ーー今後の展望について教えてください。
総理大臣杯の結果を受けて東海学生リーグの他大学さんも警戒してくると思います。それを受けて立ってしまってはダメだと思うのでどれだけ自分たちがまだまだ圧を持って挑戦できるかだと思います。見てるみなさんがワクワクする試合をしようと言っているのでそのような試合が1試合でも多くできるといいなと思います。また、関東関西の伝統のある強豪校と本当の意味で肩を並べることができる伝統校になりたいです。今シーズンに関しては残りのリーグ戦を優勝してインカレに挑戦。そしてこの夏に埋まらなかったものがどれだけ埋まっているのか、そこに尽きますね。